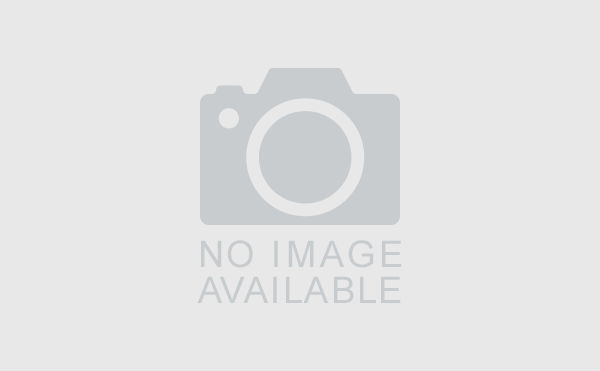オーナー様への手紙:その「借金」が本当に相続税対策ですか?〜不動産評価のカラクリを理解する〜

さて、今回の「オーナー様への手紙」では、相続税対策としてよく耳にする「借金が相続税対策になる」という言葉の真意**について、深く掘り下げていきたいと思います。巷には「借金すれば相続税対策になります!」と自信満々に語る営業マンがあふれていますが、その言葉の裏にあるカラクリを理解しないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
1.「借金が相続税対策になる」は本当か?〜その言葉の真意を問う〜
「借金すれば相続税対策になります!」
この言葉を聞いて、「なるほど!」と納得される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私はこの言葉を聞くと、いつもこう問いかけます。
「なぜ借金したら相続税対策になるのですか?」
この質問に、はっきりと、そして論理的に答えられる営業マンは、残念ながらそう多くはありません。なぜなら、「借金そのものが相続税対策になるわけではない」からです。
相続税の計算において、被相続人の財産から債務(借金)を差し引くことができるのは事実です。例をあげます。1億円の財産を持つ方が5,000万円の借金を抱えていれば、相続税の計算上は5,000万円の財産として扱われるため、一見すると借金が相続税を減らす効果があるように見えます。
しかし借金がなければ財産は5,000万円となり、結局同じです。
つまり、借金をして現金を保有しているだけでは、相続税対策にはならないのです。
では、なぜ「借金が相続税対策になる」という話が出てくるのでしょうか? その答えは、「借金をして、その資金で不動産を購入する」という一連の流れにあります。
2.相続税対策の肝は「資産の評価額を下げること」
相続税対策で本当に重要なことは、「相続財産の評価額を下げること」です。そして、その有効な手段の一つが、「現金を不動産に変えること」なのです。
仮に、借金した1億円の現金の価値は1億円です。しかし、この借金した1億円で不動産を購入すると、不動産の実際の価値は1億円でも、相続税を計算する際の評価額は30%程度減となり7,000万円程度となることがあります。
上記の通り、元々現金をお持ちの方は、わざわざ借入をせずとも、その現金で不動産を買うことで節税効果が得られます。つまり、「現金を不動産に変えると相続税が安くなる」のであって、「借金すること自体が相続税が安くなる」わけではないのです。
不動産、特に土地や建物は、相続税を計算する際の評価額が、時価よりも低く評価されるという特性があります。この「評価額の引き下げ効果」こそが、相続税対策の肝なのです。
① 土地の評価額
土地の相続税評価額は、一般的に時価の80%程度で評価されます。
② 建物の評価額
建物の相続税評価額は、建築費の50%〜70%程度とされており、時価よりも大幅に低く評価されます相続税評価額(固定資産税評価額)は極めて低くなります続税評価額(固定資産税評価額)は極めて低くなります(古い建物となれば評価額は極めて低くなります)。さらに、賃貸用の建物であれば、「貸家建付地評価減」や「借家権割合」といった特例が適用され、評価額をさらに引き下げることが可能です。
この評価減のカラクリこそが、「借金をして不動産を購入することが相続税対策になる」と言われる所以なのです。借金で手元に増えた現金を、評価額の低い不動産に変えることで、相続財産全体の評価額を圧縮し、結果として相続税の負担を軽減するというスキームです。
3.「なんで借金したら相続税対策になるの?」と聞いてみよう!
もし、あなたの目の前に「借金すれば相続税対策になります!」と力説する営業マンが現れたら、ぜひこう質問してみてください。
「なんで借金したら相続税対策になるんですか? 借金そのものが相続財産から控除されるのは分かりますが、その借金で得た現金は相続財産になりますよね? 具体的にどういう仕組みで相続税が安くなるんですか?」
この質問に対して、
- 「債務控除ができるからです!」
- 「手元に現金が残らないからです!」
といった漠然とした答えしか返ってこないようであれば、その営業マンは「不動産の評価額が下がる」という本質を理解していない可能性があります。
本当に相続税対策を熟知している営業マンであれば、
「(手持ち現金を使う使わないを考慮しないとして)借入金で不動産を購入することで、現金の評価額が、時価よりも低い不動産の評価額に変わります。特に、賃貸不動産であれば、土地や建物の評価額がさらに引き下げられるため、相続財産全体の評価額を圧縮し、結果として相続税の負担を軽減することができます。しかし手元に現金がある場合は無理に借入をする必要はありません。」
といったように、不動産の評価額が下がるメカニズムについて、具体的に説明してくれるはずです。
4.借金は「手段」であって「目的」ではない
相続税対策における借金は、あくまで「評価額の低くなる不動産を取得するための手段」であって、「借金そのものが相続税対策の目的」ではありません。
安易な借金は、将来の返済負担や金利変動リスク、不動産価値の下落リスクなど、様々なリスクを伴います。特に、高齢になってからの多額の借金は、ご自身の生活を圧迫する可能性もゼロではありません。私もファイナンシャルプランナーとして、お客様のライフプラン全体を考慮した上で、無理のない資金計画を立てることの重要性を常々お伝えしています。
相続税対策は、単に税金を安くすることだけが目的ではありません。残されたご家族が、円滑に財産を承継し、安心して暮らしていけるようにするためのものです。そのためには、目先の節税効果だけでなく、長期的な視点に立ち、ご自身の資産状況、ご家族の状況、そして将来のライフプランを総合的に考慮した上で、最適な対策を講じる必要があります。
5.専門家との連携が成功の鍵
相続税対策は、非常に専門的な知識を要する分野です。不動産、税務、法律など、多岐にわたる知識が必要となります。
- 不動産会社:不動産の選定、賃貸経営のサポート
- 税理士:相続税の計算、節税対策の提案
- 司法書士:遺言書の作成、遺産分割協議のサポート
これらの専門家と連携し、それぞれの専門知識を最大限に活用することが、相続税対策を成功させるための鍵となります。
相続税対策は、早めに取り組むほど選択肢が広がり、効果的な対策を講じることができます。もし、ご自身の相続税対策についてご不安な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。